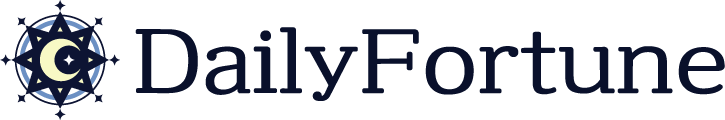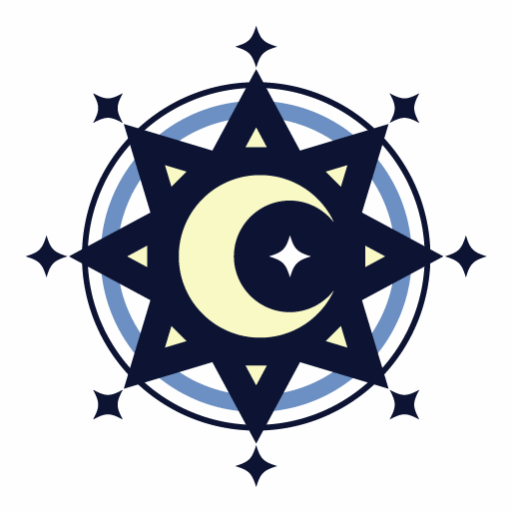彼岸花は万葉集にも登場するほど古くから人の生活の側にある植物です。獣害対策として墓地に植えられたため、死を連想するような別名を多く持っています。
一方で独特の生態と花の美しさを称える別名も多いです。花言葉も形状や生態から連想した前向きなものから、墓地に咲くことから連想される悲しいものまで多種多様です。
今回は多様な別名と花言葉を持ち、少し変わった生態を持つ彼岸花を余すことなくご紹介します。ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
彼岸花の花言葉の由来や言い伝え

「彼岸花」という名称は、秋のお彼岸のころに咲くことが由来となっています。花言葉はたくさんあり、「悲しき思い出」「諦め」「独立」「情熱」と、ネガティブなものからポジティブなものまで多様です。
さらに彼岸花には別名もたくさんあり、言い伝えも豊富です。
花の色は赤を基本に、白、黄色、ピンクなどがあります。花の咲く時期に葉はなく、花が咲き終わった後に細くて光沢のある葉っぱがでてきます。
開花の際には地面から緑色の花茎だけが伸びます。その上に雄蕊が長く、花弁の細い反り返った百合のような花が、束ねたように咲きます。
彼岸花は墓と縁が深く、また毒もあるため、縁起が悪いという風潮があります。いっぽうでその美しさや救荒作物、獣害対策として重宝もされてもきました。
日本の彼岸花は3倍体のため、種を作りません。株分けし、人の手で植えることで増えていきます。
食べると彼岸に行く
彼岸花にはアルカロイド系の毒があります。とくに鱗茎(りんけい・球根)に多く含まれ、口にすると涎や吐き気、腹痛、下痢、中枢神経の麻痺などが現れ、死に至ることもあります。
このことから、彼岸花は「彼岸(あの世)へ行く花」とも呼ばれています。こちらを名前の由来とする説もあるんですよ。
彼岸花の鱗茎は適切に毒抜きすればデンプンを取り出して食べることができますが、毒抜きが甘ければ食中毒になります。さらに葉がニラやノビル、アサツキなどに似ているため、事故が起こりやすいです。
毒草はたくさんありますが、彼岸花はとくに身近に植わっていて毒性が強いので、恐れられて、この言い伝えが広まりました。
彼岸花を摘むと死者が出る
彼岸花を摘むと死者が出てくるという言い伝えがあります。これは日本の埋葬方法の主流が土葬だったころにできた伝承です。
土葬の遺体はモグラや獣の恰好の餌食です。そこで、彼岸花を墓の近くに植えることで毒を利用し、遺体をモグラなどが掘り返さないようにしていました。
しかし、彼岸花を摘んでしまうと、毒の効果がなくなり、モグラが掘り返してしまいます。そのため、彼岸花を摘んだ場所では埋めたはずの遺体が土から上に出てしまうことがありました。これが「彼岸花を摘むと死者が出る」という言い伝えの由来です。
家に持って帰ると火事が起きる
彼岸花を家に持って帰ると火事が起きるという言い伝えがあります。これは炎のような真っ赤な彼岸花の色に由来しています。
彼岸花は切り花にしてしまうとあっという間に萎れ、日持ちしません。さらに毒があります。昔はモグラ除けや救荒植物としても重宝されていました。そのため、彼岸花を意味なく摘み取るのはよくありません。
子どもなどが面白半分に彼岸花を荒らさないように戒めるために生まれた言い伝えとも言われています。
墓地に彼岸花が咲く理由

彼岸花は墓地に多く植えられています。これはモグラやネズミ、獣などが死者を荒らさないためでした。
日本は昔、火葬ではなく土葬が一般的でした。これを狙ってモグラやネズミ、獣などがでることがあります。しかし、彼岸花を植えると、毒を嫌って、モグラなどが寄り付かなくなります。墓地に彼岸花が多いのは、遺体を守るためです。
また彼岸花はお墓参りが多くなる彼岸の時期に花を咲かせます。そのため、墓地と彼岸花のイメージがより強く結びつくようになりました。
彼岸花の別名
彼岸花には別名が1,000種類以上あります。ここでは代表的な別名である曼殊沙華、地獄花、親知らず、南無阿弥陀仏、天蓋華、死人花など、6種の呼び名の由来を説明します。
彼岸花がここまで多くの別名を持っているのは、古くから広い地域で人々の生活に根付いていた証拠です。
そして、彼岸花の別名に仏教用語や不吉な言葉、死を連想させるようなものが多いのは、花の美しさや毒の危険性、独特の生態などを反映しているからです。
曼珠沙華(マンジュシャゲ)
曼殊沙華は仏教用語です。法華経などの仏典からきています。
サンスクリット語には「manjusaka」という言葉があり、こちらは「天界に咲く花」「赤い花」「葉より先に咲く赤い花」などを意味します。そのサンスクリット語に漢字を当てはめると、曼殊沙華となります。
また、仏教の経典である「法華経」を釈迦が説いたのを祝って、曼殊沙華を含む花々が空から降ってきたと言われています。
彼岸花の赤くて独特の形状の形の花は「天上」のイメージにぴったりです。
地獄花(ジゴクバナ)
彼岸花の開花時期はお彼岸の頃です。仏教では「あの世とこの世が近づく時期」とされています。
あの世の世界の1つである地獄が近い時期に咲くこと、そして墓地に多く咲いていることが地獄花という別名がついた理由です。
親知らず
彼岸花は花と葉を同時に見ることができません。
冬から春にかけて葉を茂らせて栄養を溜め、秋になると花茎だけを伸ばして開花をします。
花は、花を養う葉(親)を知らないため、親知らずという別名がつきました。
南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏は仏教用語で、仏への帰依を意味しています。
彼岸花を食べると、毒に当たり、死んでしまうことがあります。
「あの世に行く」すなわち、すなわち、「ホトケになる」という意味で「南無阿弥陀仏」という別名がつきました。
天蓋花(テンガイバナ)
天蓋とは、祭壇などの上部の覆いの装飾を意味します。仏教では、身分の高い人や仏像などを日差しなどから守るために天蓋を使用することがあります。
その天蓋の形状が彼岸花の花に似ているため、この別名になりました。
死人花(シビトバナ)
墓地によく咲いている、彼岸のころに咲く、毒を持っているなど、彼岸花には死をイメージする要素がたくさんあります。
また、昔は飢饉になれば、彼岸花の鱗形を毒抜きするとはいえ、食べなければなりませんでした。
死に近い場所にある花ということで、死人花という別名がつきました。
彼岸花とリコリスの違い

リコリスはヒガンバナ科ヒガンバナ属全般の植物を意味しています。彼岸花はそのリコリスの1つに含まれます。
リコリスは東南アジアを中心に分布し、彼岸花のほか、キツネノカミソリ、インカルナータ、ナツズイセンなど20種ほどあります。花の色は赤系、黄色系、白系が多く、花弁が細いという特徴があります。
彼岸花はリコリスの1種という位置づけです。しかし、日本では彼岸花がリコリスの代表的な植物なので、「リコリス」がそのまま彼岸花を指す場合もあります。
彼岸花の咲く時期
彼岸花の開花時期は9月中旬から1週間くらいです。お彼岸の頃合いになるといっせいに花茎を伸ばし蕾を膨らませ、そして咲きます。分布は北海道と東北地方を除く日本全国です。
彼岸花は自然交配では増えないので、咲く場所は基本的に人の手の入っている場所です。街路沿い、田畑のあぜ道、庭先、墓地周辺、公園などでよく見られます。
彼岸花のいい意味の花言葉

彼岸花には別名だけでなく、花言葉も多くあります。彼岸花は死を連想させるような不吉な逸話が多くありますが、前向きでいい意味の花言葉もあります。
情熱
彼岸花にはカラーバリエーションがありますが、代表的な花色は赤です。
花の形状も炎に似ているので、燃え立つような情熱を感じさせるのが花言葉の由来です。
独立
彼岸花の開花時期には葉が生えていません。
葉や茎を伴わず、花茎だけを伸ばして咲いている姿から、何者にも頼らない凛とした独立のイメージを想起させます。
彼岸花が墓地にゆかりが深いことから「故人に頼らずに独立をする」という意味もあります。
彼岸花の怖い意味の花言葉

彼岸花には恐い意味の花言葉もあります。死をイメージする逸話が多いためです。
悲しい思い出
彼岸花は墓地に多く植えられているため、墓参りを連想させます。
故人を忍ぶ、つまり悲しい思い出が蘇ることからこの花言葉になりました。
あきらめ
彼岸花には死のイメージが強くあります。死とは、どうやっても覆せないものです。
つまり、どれほど未練があっても諦めなければならないという意味になります。
彼岸花の色別の花言葉
彼岸花は白、黄色、赤、その他、花の色によって花言葉が違います。色による花言葉の違いを知れば、たとえば彼岸花の写真を相手に贈る時などにその想いを乗せることも可能になります。
彼岸花そのものの花言葉に加えて、白は一途さ、黄色は元気さ、赤は強さを連想させる花言葉となっています。
彼岸花の花の色で代表的なのは赤ですが、他の色の花言葉の意味も味わい深いですよ。切り花としての寿命は短く、またポジティブな花言葉があるとはいえ、「墓地」のイメージが強いので、一般的な贈り物として向いている花ではありません。
しかし、モチーフとして使う機会もあるので、意味を知っておいて損はないですよ。切り花も、売っているお花屋さんもあり、部屋に飾ってOKです。ただし、切り花の水には毒の成分が溶け込むので、小さなお子さんやペットが飲まないように注意する必要があります。
 白
白-
「また会う日を楽しみに」「想うはあなた1人だけ」
 黄色
黄色-
「陽気」「元気」「深い思いやりの心」「追憶」「悲しい思い出」
 赤
赤-
「情熱」「再会」「また会う日を楽しみに」
白色の彼岸花

また会う日を楽しみに 想うはあなた1人だけ
彼岸花の開花時期が年に1回、決まった時期だけ開花するという生態と、白の持つ一途さや純粋さというイメージが由来の花言葉です。
白色の彼岸花は他の色に比べて、とくに別離のイメージが強いです。
離れている人へのお手紙などに写真や絵で添えるのもおすすめです。
黄色の彼岸花

陽気 元気 深い思いやりの心 追憶 悲しい思い出
黄色の持つポジティブなイメージと、炎に似た花の形状に由来する前向きで明るい花言葉です。近況を伝える手紙などに。
そして彼岸花の墓参りのイメージと黄昏の色に由来する少し寂しい花言葉もあります。
少し寂しい気持ちを分かってほしい時に添えてみては。
赤い色の彼岸花

情熱 再会 また会う日を楽しみに
赤という、燃えたつような色と花の形状からくる花言葉です。意欲に満ちた姿勢を伝えられます。
また、彼岸花の花が咲くのは1年のうち、1回、限られた時期だけです。しかし毎年必ず咲くので、再会やまた会う日を楽しみにするイメージがあります。遠くに行ってしまう人などに絆を示すために使えます。
青色・ピンク・紫色・黒色

これらの色の彼岸花には特別な意味の花言葉はありません。
そのため「情熱」「独立」「悲しき思い出」「あきらめ」など、通常の彼岸花と同じ花言葉を持ちます。
青色や紫色、黒色などの彼岸花は一般には流通すらしていません。
彼岸花の基本情報まとめ
- 花言葉
-
悲しき思い出」「諦め」「独立」「情熱」
- 由来
-
縁起が悪いという風潮、美しさや救荒作物、獣害対策として重宝
| 植物分類(科・属) | ヒガンバナ科・ヒガンバナ属 |
| 原産国 | 中国大陸 |
| 和名 | ヒガンバナ |
| 英名 | red spider liliyまたはspider liliy |
| 咲く時期 | 9月中旬から1週間程度 |
| 切り花の日持ち日数 | 数日程度(切り花にはあまり向きません) |